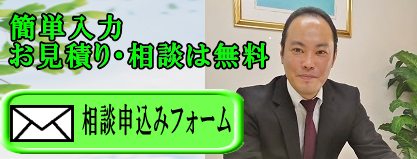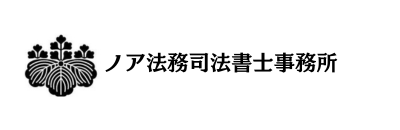目次
1. 設立方法は2種類 ~株式会社設立前の基礎知識②~
会社の設立方法には発起設立と募集設立の2つの方法があります。
発起設立とは発起人(会社を作ろうと言いだした人)がすべての株式を引き受けて設立する設立方法です。募集設立に比べて手続が簡易ですので、小さな会社の設立方法として一般的です。
発起人自身が必ず出資しますので、発起人は設立時株主となります。
募集設立とは発起人以外からも出資してもらい、不特定の第三者から資金を集める設立方法です。設立手続きは厳格な手続きが必要です。
2.株式会社の役員~株式会社設立前の基礎知識~
会社法上、取締役、監査役、会計参与の事を株式会社の役員と言います。
小規模な株式会社の場合自分1人が株主となり、役員である取締役を兼ね、自動的に代表取締役も兼ねて会社を設立することが出来ます。
(1) 取締役
取締役とは会社の経営を行う人です。最低1名必要となります。
法人、成年被後見人、成年被保佐人等の人は取締役になることが出来ません。未成年者も親の同意があれば取締役となることが出来ます。
任期は原則2年ですが、任期を10年まで定款で伸長させることが出来ます。家族が役員になる場合等には任期を10年にした方が、役員変更の登記を長期間する必要がありませんので、費用的にはお勧めと思いますが、途中で解任した場合には役員からの損害賠償請求の恐れもあります。
取締役は会社と類似の取引をしてはならない規制や会社と直接取引してはいけない規制等があり、会社に損害を与えると会社から損賠賠償請求される責任を負っています。
取締役は株主総会で選任されます。尚、設立時取締役は発起人の議決権の過半数や定款に記載して選任します。
(2) 監査役
監査役とは取締役の行為が法律や株主総会決議に反してないか、決算書の内容が適正かどうかを監視する事を業務とします。基本的に監査役を置くがどうかは任意であり、小規模な会社では置かないのが一般的と言えます。
もっとも、取締役会の設置をする場合には原則的には監査役を置く必要があります。この場合は1人いれば足ります。
取締役と同様監査役も法人、成年被後見人等の人は就任する事が出来ません。その他にその会社や子会社の取締役や支配人等の人は監査役に就任することが出来ません。
監査役の任期は4年ですが、取締役同様任期を10年まで伸長させることが出来ます。
監査役も任務を怠っていた時等は会社に対して損害賠償の責任を負います。
監査役は株主総会で選任されます。
(3)会計参与
会計参与とは取締役と共同して計算書類を作成する事を業務とします。会計参与を置くかどうかは任意であります。会計参与を置く場合は1人いれば足ります。
公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人でなければ、会計参与になることは出来ません。
任期は原則2年で、取締役、監査役同様、任期を10年まで伸長させることが出来ます。
会計参与もその任務を怠っていた時は会社に対して損害賠償の責任を負います。
会計参与は株主総会で選任されます。
会計参与を置くことによって、計算書類の正確性に努める態勢を示して、会社の信頼が増し、融資・出資に営業を与える事が出来ると言えます。
3.株式会社の機関について~株式会社設立前の基礎知識~
取締役(会)、株主総会、代表取締役、監査役の事を会社法では機関と呼びます。
会社にどの機関を置くかを決める事を機関設計と言います。
この機関設計は会社法上様々なパターンがあります。
必須機関は株主総会と取締役であり、これにどの機関を足すかによっておよそ40通りほどの組み合わせがあります。
(1) もっとも簡易な小規模会社パターン
必須機関である株主総会と取締役だけ置く機関設計です。取締役会、監査役を置きません。
1人株主が取締役となる事により、会社の意思判断がすべて一人で出来ますので、経営判断の機動性に優れていると言えます。
反面、株主が複数の場合等には会社の意思決定は株主総会で決定する必要がありますので、機動性に欠けるデメリットもあります。
対外的なイメージもそこまで望めないかもしれません。
(2)中小企業向け取締役会設置パターン
原則として取締役会を設置するには取締役が3人必要であり、又監査役の設置も必要です。
この機関設計により、株主が複数であっても経営の意思判断等は取締役会で行うことが出来ますので、小規模会社パターンのデメリットを避けることが出来ます。
又、監査役を置くことによって、経営体制強化の姿勢を示すことにより、対外的に良いイメージを持たれ、融資・出資が期待できると言えます。
反面、最低4人の役員が必要ですので、人数を集めるのが大変ですし、役員報酬等の資金面でのデメリットがあります。
3.株式会社の設立における専門家の役割~株式会社設立前の基礎知識~
会社の設立は書類作成、定款認証、設立登記、その後の税金等の手続き等すべてご自身でなさることも出来ます。
もっとも、すべての手続き等をご自身でやるのは多大な労力がかかりまして、設立に向けた営業準備に力を入れる事ができないデメリットはあると思います。
(1)会社設立前に関与する専門家
として、司法書士と行政書士がおります。
司法書士は書類作成から定款の認証手続、会社設立登記と言う株式会社設立手続き全般に関与できます。
行政書士は書類作成、定款の認証手続を行なえますが、登記申請をすることが出来ません。もっとも各種許認可が必要な会社においては、許認可等の申請で関与が必要となります。
(2)会社設立後に関与する専門家
会社設立後に関与する専門家としては税理士と社会保険労務士がおります。
税理士は法人税の決算申告、帳簿の作成で関与します。
社会保険労務士は人事労務に関する手続きで関与します。就業規則の作成、給与計算等です。
当事務所提携士業と協力しまして、すべての株式会社手続きにつき対応致します。
4.許認可が必要な事業~株式会社設立前の基礎知識~
株式会社は基本的には許認可を必要とせず自由に事業を行うことが出来ます。
もっとも、行政庁の許可を得なければ、事業を行なえない業種もあります。
資格が必要な業種や、一定の資本金が必要な業種、一定の営業面積が必要な業種があります。
せっかく会社を設立したのに、許認可を考慮せず、営業がはじめられない事もありますので、注意が必要です。
許可が必要な業種
許可とは通常は禁止されているが、要件を満たしたものだけが事業を行うことが出来ます。
- 飲食店、レストラン、喫茶店 (保健所)
- 古物商、質屋業(警察署)
- 労働者派遣業・有料職業紹介事業(労働局)
- 建設業(建設業課)
- 風俗営業(スナック、パチンコ)(警察署)
登録が必要な業種
- 倉庫業(地方運輸局)
- 貸金業
届出が必要な業種
届出書を提出するだけで、その事業を行なえます。
- 美容院・クリーニング店 (保健所)
- ペットショップ
免許が必要な業種
- 酒類販売(法人課税担当)
- 宅地建物取引業(不動産課)
当事務所提携士業と協力しまして、許認可を含むすべての株式会社設立につき対応致します。