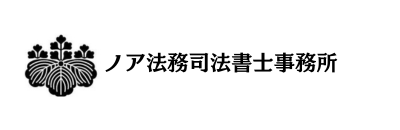目次
- 1 遺産分割協議はかならずしなければいけないのか?
- 2 相続分の決め方
- 3 よくある質問
- 3.1 戸籍謄本や住民票に3ヶ月とかの有効期限ありますか?
- 3.2 戸籍謄本等は返却されるのか?
- 3.3 登記事項証明書に旧住所が記載されている場合住所移転の登記が必要か?
- 3.4 登記識別情報又は権利証を紛失しました相続登記は出来ますか?
- 3.5 遺産分割協議書の参加者は?
- 3.6 行方の分からない相続人が居る場合
- 3.7 相続人が遠方に住んでます、遺産分割協議でわざわざ集まる必要ありますか?
- 3.8 未成年も遺産分割に加われますか?
- 3.9 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は全員分ですか。
- 3.10 印鑑証明書に期限はありますか?
- 3.11 特別受遺者を抜かして遺産分割協議は出来るか?
- 3.12 遺言書による相続登記の場合
- 3.13 相続登記を相続人別々で申請できるか?
遺産分割協議はかならずしなければいけないのか?
相続は
- 遺言書がある場合それに従い、相続登記します。
- 遺言書が無い場合共同相続人全員の合意による遺産分割協議で相続登記します。
- どちらもない場合、一般的に法定相続分の割合で相続登記します。
ですので、必ずしも遺産分割は必要とは言えませんが、遺産分割協議で不動産を単独所有、又は少人数で共有するのが一般的と言えます。
相続分の決め方
相続分は
- 遺言による指定で決まります
- 遺産分割協議で決めることも出来ます
- いずれもない場合民法の規定による法定相続分で決まります。
| 相続人 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 (親の事です) | 兄弟姉妹 |
| ①配偶者と子供 | 2分の1 | 2分の1 | ||
| ②配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 | ||
| ③配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 | ||
| 子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数の場合各相続分を頭割りで等分します。 例えば子供が2人の場合は2分の1×2分の1で子供1人の相続分は4分の1となります。 | ||||
よくある質問
戸籍謄本や住民票に3ヶ月とかの有効期限ありますか?
有効期限はありません。
戸籍謄本等は返却されるのか?
戸籍謄本等は「相続関係説明図」を添付すれば登記完了後に返却されます。
登記事項証明書に旧住所が記載されている場合住所移転の登記が必要か?
この場合住所移転の登記は省略できます。
この場合住所移転の経緯が分かる除住民票、戸籍の附表の写しの添付が必要です。
登記識別情報又は権利証を紛失しました相続登記は出来ますか?
相続による移転登記の場合には権利証(登記済証)又は登記識別情報の提供は不要です。
遺産分割協議書の参加者は?
遺産分割は相続人全員の合意が必要となります。
尚、相続放棄した者は相続人ではもはやないので、遺産分割に参加する必要はありません。
行方の分からない相続人が居る場合
この場合、行方が分からないからと言って残りの相続人だけで遺産分割は出来ません。
相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、その管理人と遺産分割協議をすることになります。
相続人が遠方に住んでます、遺産分割協議でわざわざ集まる必要ありますか?
原則、一堂に会して協議が望ましいです。
しかし、遺産分割協議書を持ち回りで全員が承認する方法でも構いません。
又同一内容の分割協議書を相続人分作成してそれに各自署名押印して一通の遺産分割協議書とすることも出来ます。
未成年も遺産分割に加われますか?
親権者である配偶者と未成年の子供で遺産分割をする場合、
親権者である配偶者と未成年の子供が遺産分割協議をするのは利益相反行為(お互いの利益がぶつかる事)となりますので
親権者は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなくてはなりません。
そして、親権者と特別代理人とが遺産分割協議をすることになります。
子が複数いる場合には、未成年者1人ごとにに別の特別代理人の選任が必要です。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は全員分ですか。
遺産分割協議書を添付して相続登記の申請をする場合には、相続登記の申請人以外の協議者は遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があります。
申請人は遺産分割で不動産を取得する者となりますので、それ以外に不動産を取得出来ない者の印鑑証明書を添付することにより、遺産分割協議書が真実のものであることを担保するためです。
印鑑証明書に期限はありますか?
想像登記に使用する、印鑑証明書は発行後3ヶ月を過ぎても構いません。
発行日が死亡以前のものでも遺産分割協議書作成以前でも構いません。
但し、金融機関などの他の相続手続きの場合は、印鑑証明書につき6カ月等の期間があります。
特別受遺者を抜かして遺産分割協議は出来るか?
特別受益者の参加が無くても遺産分割協議をすることが出来ます。
この場合、特別受益者(亡くなった方から贈与等を受けてその価格が自分の相続分より多いので相続分が無い者)の特別受益証明書に実印、印鑑証明書も相続登記の添付書類となります。
遺言書による相続登記の場合
遺言書がある場合相続人の戸籍謄本と被相続人(亡くなった方)の死亡記載のある戸籍で構いません。 被相続人の出生からの戸籍は不要です。
相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。
尚、遺言書が自筆証書遺言の場合でしたら、検認を得てないと当該遺言書を添付しても相続登記は出来ません。
相続登記を相続人別々で申請できるか?
例えば、子供二人が別々に相続登記出来るか(所有権一部移転と残りの持分移転登記を相続を原因として移転)と言う事ですが、
出来ません。
この場合一件の申請書でする必要があります。