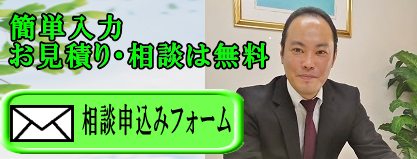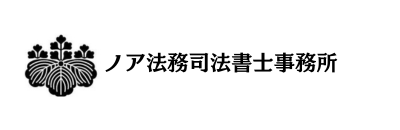高齢者の財産管理は、将来の認知症や身体的な制約に備えるため、早期の対策が重要です。以下に代表的な方法とその特徴をまとめました。
高齢者の財産管理方法は、個々の状況や希望に応じて選択することが重要です。専門家と相談し、最適な対策を検討してください。
目次
1.成年後見(法定)とは (主に形式的管理業務)
判断能力が不十分になった者 (認知症者)の保護のために、法律行為・事実行為両面においてサポートを行う制度である、
(1)事務の内容
財産の調査及び目録の作成(853条)、被後見人の意思尊重義務、身上配慮義務(858条)、被後見人の財産の管理及び代表(代理)(859条)などが挙げられている。
「事務」とは法律行為のことであり、被後見人を実際に介護することなど事実行為を後見人自身が為すことは事務には含まれない。
〇財産管理
〇預貯金通帳の保管及び手続。
〇身上監護
〇病院等の入退院に関する契約。
(2)特徴
〇 裁判所への申立で後見人選任。よって後見人の権限が強いし金融機関等への代理手続きも必ず認められる。
〇 親族後見で申し立ててその他資格業の後見人が選任されても取り消せないという不都合
〇 一度選任したら終身。資格者後見人への毎月の支払があり。
〇 また親族後見人が選任されても裁判所選任の後見監督人が付く可能性も高い。、監督人に対して月々の支払が生じる
(3)凡その費用
申立費用で15万~20万程
2.任意後見 (家族を事前に後見人に)
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
(1)事務の内容
基本的に法定後見と同じ(ご自身でより細かい内容を決められる)
(2)特徴
〇 認知症等になったら契約内容発動
〇 法定後見で認められづらい親族後見人などを事前に指定
〇 もっとも、後見監督人がついてしまいます。監督人に対して月々の支払が生じます。監督人選任申立が必要となります。
(3)費用
公正証書で財残管理任意後見契約書作成 15万~20万
3.財産管理契約(委任契約) どちらかと言えば将来の紛争予防
財産管理契約とは、自分が委任する人に対して、自己の財産管理に関する業務を委託してその人に代理権を与える契約のことをいいます。
高齢者に判断能力がある場合には「成年後見制度」は利用することはできません。
そこで、判断能力が年相応で問題がないものの手足や目が不自由である場合に、家族や第三者に財産管理を変わってやって欲しいというときに、この「財産管理契約」がよく利用されています。
(1)事務の内容は本人で自由に
(2)特徴
〇 後見人に比べて信用度は低いので、施設や金融機関等が財産管理人を認めるかは金融機関等による。メガバンク等は認められやすいが、独自の委任状等も必要。
〇 公正証書で作成すれば少しは信用度が上がる。
例えば高額な口座を引落などの場合、基本的に本人が行くが、この財産管理契約書を持って、本人は電話のみでなど対応の変化も見込める。又代筆なども認められやすい。
〇 他の相続人に勝手に委任者(高齢者)の財産を使用してないとの法的裏付けになる。
(3)費用
凡その費用 任意後見と合体型で15万~20万程
4.(家族)信託契約 管理のみならず処分運用が可能
他人 (受託者 ) に一定の目的に従って財産の管理または処分を行わせることを目的として,受託者に財産権の移転その他の処分をすること
財産所有者(委託者)が金銭,有価証券,不動産などの財産(信託財産)を財産権の移転・設定によって他人(受託者)に管理・処分させ,その利益を自己または指定する者(受益者)に交付させることを委託する契約。
詳しくは家族後見へ
費用
事案や作成する契約に自由度が高く、内容により大きく異なりますが35万~
5.各手続まとめ
〇後見等契約時等に本人の意思能力がある場合
法定後見×(※そもそも意思能力あるので、法定後見の問題ではない)
任意後見○
財産管理契約〇
信託契約〇
〇後見等契約時等に本人の意思能力がない場合
※意思能力が無ければそもそも契約を結べません。
法定後見〇
任意後見×
財産管理契約×
信託契約×
〇実際の管理処分時に本人の意思能力がある場合に後見人・受任者の行為は可能か
法定後見×(そもそも意思能力があるので後見が発動してない)
任意後見×(そもそも意思能力があるので後見が発動してない)
財産管理契約〇
信託契約〇
〇実際の管理処分時に本人の意思能力がない場合ば後見人・受任者の行為は可能か
法定後見〇
任意後見〇
財産管理契約△※本人確認が取れないので金融機関等が認めない可能性
信託契約〇※財産は受託者に移転している
本人・委託者が締結した契約を後見人・受託者・委任者が取り消しできるか
法定後見〇
任意後見× ※任意後見人には取消権が無い。代理としてクーリングオフや消費者契約法で対処
財産管理契約×
信託契約△ ※(無効、既に委託者の財産ではないと言える財産について契約しているので)
家族以外の関与が必要か
法定後見 必要 ※基本的に家族以外が後見人となる。家族が後見人でも後見監督人は家族以外がなる。
任意後見 必要 ※後見監督人は家族以外がなる
財産管理契約 不要
信託契約 不要
介護契約や介護施設への入所契約を後見人、受任者受託者が結べるか
法定後見〇
任意後見〇
財産管理契約〇 ※後見と異なり、本人の意思能力があるとき限定で可能となる可能性があるが相手方(施設等)の個々の判断による
信託契約× ※受託者は本人の代理人ではないから
本人死後まで認められるか
法定後見×
任意後見×
財産管理契約△ ※死後事務委任
信託契約〇
公正証書での契約作成は必要か
法定後見 不要 ※裁判所に対する申立
任意後見 必要
財産管理契約 不要 ※不要だか作成が望ましい
信託契約 不要 ※不要だが作成が望ましい
本人認知症発症後の本人の財産の運用相続対策はできるか
法定後見 ✖ ※後見人は運用できない、基本的に管理処分
任意後見 ✖ ※同上
財産管理契約 ✖
信託契約 〇 管理処分に留まらず、運用処分も可能
後見人・受託者の義務
法定後見 〇 ※法律で決まってる
任意後見 〇 ※法律で決まってる
財産管理契約 △ ※契約内容による
信託契約 〇 ※法律で決まっている
本人の居住不動産売却に裁判所の許可は必要か
法定後見 必要
任意後見 不要
財産管理契約 ✖ ※そもそも財産管理人は不動産売却できない
信託契約 ✖ ※ 受託者に移転しているので不要
意思能力のある高齢者の預金の管理や詐欺契約等の阻止の考察
1.預金の管理について
① 法定後見の場合
そもそも現時点で意思能力あるなら本人が契約当事者なので阻止は不可
② 任意後見の場合
現時点で意思能力あるので、任意後見契約を結べるが、認知症等が発動してないので本人が契約当事者なので阻止は不可
③ 財産管理契約
管理契約は結べる、通帳は名義変更不可、通帳を預かることにより勝手な引出し等は出来ないが、(管理契約を結ぶことにより他の相続人に勝手に使ってない事を証明。他の相続人対策)
取消権が無いので詐欺的契約は取り消せないので、阻止は不可
④ 信託契約
信託契約は結べる、通帳は金融機関によっては信託受託者として口座を作成。
(メガバンクは非対応、信金は対応が進んでおります)
通帳カードも受託者へ・詐欺契約は信託財産なら防げる可能性が高い(そもそも本人の財産は受託者へ移転しているので)。
委託者は行為能力を失わないので、契約自体 詐欺的契約の阻止は無理です。
勝手に高額リフォーム契約は出来てしまいます。
しかし、すべての現金を信託財産として相手方の差し押さえ等を防ぐなどの 手立てはあり。