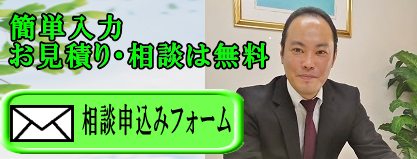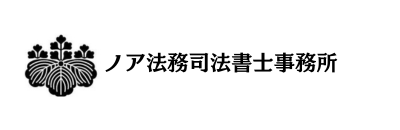1.設立費用 ~株式会社設立準備~
確かに、会社法によって資本金は1円でも株式会社は設立できるようになりました。
もっとも、そうだからと言って1円で会社が作れるわけではありません。
会社の設立には定款認証代、登録免許税、印鑑代等必要となります。
これらを考慮すると株式会社設立には最低凡そ30万円準備する必要があると言えます。
これに、司法書士に依頼して会社設立する場合として凡そ10万円かかります。
もっとも、電子定款を使用しますと、定款の収入印紙代4万円が節約されますが、電子定款をご自身でやられますと専用ソフトなどでかえって費用が高くなります。
費用内訳としましては
定款認証(凡そ10万)
株式会社を設立するには定款の認証が必ず必要となります。
この認証手数料として公証役場に支払う金額として5万円(資本金によって異なる),印紙代として4万円(電子定款の場合不要)又定款謄本取得手数料として凡そ2000円かかります。
登記申請(凡そ15万)
株式会社を設立するには法務局において登記申請が必要となります。
登記の申請において登録免許税を支払う必要がありますがこれは最低15万円です。
資本金の額が2000万以上の会社でしたらこの額より多くかかる事もあります。
その他
株式会社を設立しまして、銀行口座の開設や官庁への届け出等には株式会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が必要となる場合が数多くあります。
このため、登記簿謄本や印鑑証明書を取得する費用がかかります。
登記簿謄本は1通600円,印鑑証明書は1通450円の手数料がかかります。
又会社の実印等の印鑑作成代としましても数万ほどはかかると思います。
2.株式会社設立まで一般的に最短で10日は必要 ~株式会社設立準備~
株式会社設立の大まかな流れとしましては、
①定款作成・認証
②資本金の払い込み
③登記申請
④登記完了
の4つの流れがあります。
ここで一番時間のかかるのは登記完了でして、登記申請から一般的に凡そ10日~2週間ほどかかります。
ですので、あまり現実的でないですが、定款作成、認証をして、その日に払い込みをして、その日に申請をすれば、理論上は10日ほどで設立は完了致します。
もっとも、現実的には定款の作成をじっくり話し合ったり、登記書類を揃えたりの時間はかかりますので、ある程度事業内容、役員、資金等の重要部分が決まっている場合でも、凡そ2,3週間はかかるものと思って、余裕のあるスケジュールが必要となります。
3.まずは個人の実印登録 ~株式会社設立準備~
株式会社設立の準備としてまず初めにやるべきこととしまして、印鑑を準備する事が上げられます。
まずは個人として印鑑の登録が済んでない方は個人の実印登録が必要となります。
個人の実印は定款認証、登記申請、就任承諾等株式会社設立のあらゆる面で必要となります。
会社の実印を作る
次に会社名が決まってましたら、会社の実印を作ります。
この場合会社の名前自体が決まってない時には実印を作成しない方が良いでしょう。会社実印には会社名が入っているのが一般的だからです。
会社の実印は登記申請時に法務局に登録しますので、登記申請時には必ず必要となります。
大きさは1センチの正方形以上で3センチの正方形に収まるものでしたら四角形などでも構いませんが、一般には丸型です。
4.株式会社の概要を決める① ~株式会社設立準備~
株式会社設立の準備として、発起人は会社の名前や本店など会社の重要な内容を決めていきます
発起人とは会社を作ろうとする人の事を言います
(1)商号
商号とは会社の社名の事です。
商号のルール
- 商号中に必ず「株式会社」と入れる、前後を問わない
- 商号にはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号が使える
- 符号は6種類のみ(&)(’)(・)(,)(.)(‐)
- 英字だけの商号は認められない(定款には記載できる)
- 「~支店」「支社」等は使えない
- 「特約店」「代理店」は使える
- 「~銀行」は使えない
商号調査
会社法により類似商号は同一住所で認められないのみとなりました。
すなわち同じ商号でも同じビルではだめですが、隣のビル等ではOKとなりました。
もっとも、不正の目的で類似商号を使用することは損害賠償の恐れもありますし
特許庁に登録してある商標では、商標違反の恐れもあります
商号調査方法
- 管轄法務局で無料で商号を調査できます。
- 商標登録特許電子図書館で調べる。
(2)事業目的
事業目的とは何をしている会社なのかを一般に表示し、会社が行う事業内容の事を言います。
会社は事業目的に定めた事業以外を行うことが出来ません。
事業目的の定め方
- 明瞭かつ具体的に記載が必要 単に「商売」、「営業」などは不明確
- 営利性が必要 「ボランティア」は不可
- 将来行う予定の事業も記載
- 「各種」「等」を記載する。セミナーイベント等の企画運営、和菓子等食料品販売
- 最後に「前各号に付帯関連する一切の業務」と記載
- 許認可申請が必要な事業の場合、その記載方法には注意が必要です。
(3)本店所在地
本店所在地は基本的にどこに置くかは自由です。所在地で営業をせず、郵便物等の預りのみの場所を本店とすることも出来ます。
もっとも、許認可が必要な事業においては事務所面積も要件がありますので、そのような場合は場所の選定も必要となります。
本店所在地は定款に記載しますが、これは「東京都大田区」「神奈川県横浜市」等最少行政区のみの記載に留めるのが良いでしょう。
尚、登記申請書における本店は「東京都大田区○丁目○番○号○○ビル」等具体的に記載します。(ビル名、○号室等は省略も可能)
(4)資本金を決める
最低1円の資本金からでも株式会社は設立できます。
もっとも、資本金1円の会社では信用も得られませんし、経営も出来ません。
又資本金が許認可の要件となっている場合もあります。
- 建設業500万~
設立の際に発行する株式数に1株の発行価格をかけたものが設立時の資本金となります。
1株の発行価格は自由に決められます、1万~5万円が一般的と言えます。
ですので、資本金が決まったらそれを1株の発行価格で割ったものが設立の際に発行する株式数となります。
資本金100万円、1株の発行価格を1万円としましたら、設立時発行株式数は100株となります。
5 株式会社の概要を決める② ~株式会社設立準備~
前頁で記載しました「商号」「目的」「本店」「資本金」以外にも発起人は下記の事項を定めます。
発起人とは会社を作ろうとする人の事を言います
(1)事業年度
事業年度とは会社の会計期間の事です。
会社は決められた事業年度(会計期間)の収入、支出を計算して決算書を作ります
事業年度を4月1日~翌年3月31日として、会社設立日が平成27年6月1日の場合、6月1日~28年3月31日が第1期の事業年度となります。
事業年度のルール
事業年度は自由に決められることが出来ます。
ですが、会社設立日から最長の事業年度に設定する事が一般的と言えます。
と言うのも、例えば、会社設立が2月1日だとして事業年度を3月31日までとしましたら、わずか2か月足らずで決算期が来てしまい、設立間もない会社の無駄な負担となります。
この場合、事業年度を1月31日から2月1日までとすることにより、決算業務を1年か行わなくて済むこととなります。
(2)公告方法
株式会社は決算の内容につき公告をすることが義務となっております。
公告の方法は3種類あります。
- ①官報公告
- ②日刊新聞公告
- ③ホームページ公告
①官報公告
もっとも一般的で、費用は凡そ6万
②日刊新聞公告
大企業向け、費用は高額
インターネット公告
自社のホームページに掲載する。掲載を証明する必要があり、それに手間と費用がかかるため、小規模会社ではあまり用いられて無い。
(3)役員の選任と任期
株式会社設立の基礎知識(役員について、機関設計について)でも述べましたが、自社がどのような機関設計(取締役会を置くか等)を考えるかによって、役員の人数等は異なります。
取締役会を設置するなら取締役は3人必要ですし、原則的に監査役も必要となります。
取締役会を設置しない会社でしたら、取締役1名だけで会社は設立できます。
取締役の任期は基本2年、監査役は4年ですが、最長10年まで伸長することも出来ます。
任期を延ばすことはメリットもデメリットもありますので、それを考慮して任期を決めましょう。
(4)現物出資
現物出資とは動産や不動産を金銭の代わりに出資する事を言います。
例えば、個人のパソコン等を現物出資する場合などがあげられます。
この現物出資は500万を超える場合、手続き費用がかかりますので、500万円を超えない現物出資が一般的と言えます。
金銭で出資せずに現物出資だけで株式会社を設立する事も認められております。
(5)発行可能株式総数
会社が発行できる株式の数を発行可能株式総数と言います。
発行可能株式総数が4000株でしたら、将来的に4000株まで増やすことが出来ます。
発行可能株式総数は非公開会社では自由に決められますので、1000株、10000株でも構いません、なるべく、大きく設定するのが無難と言えます。